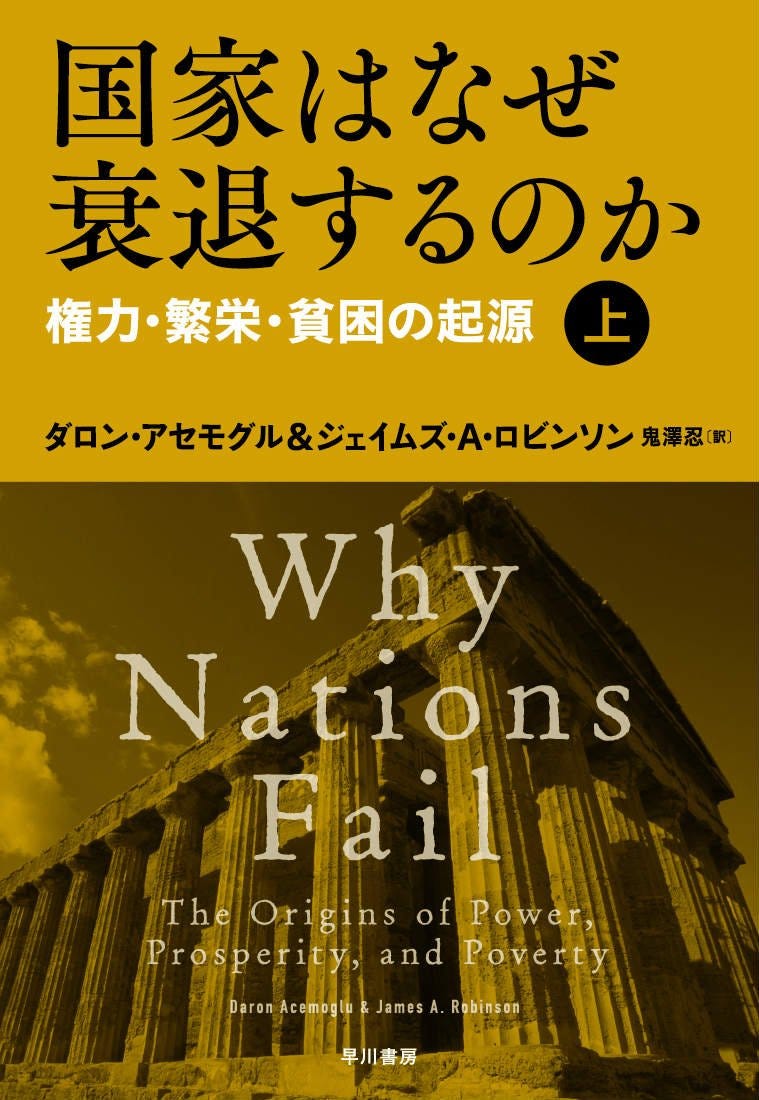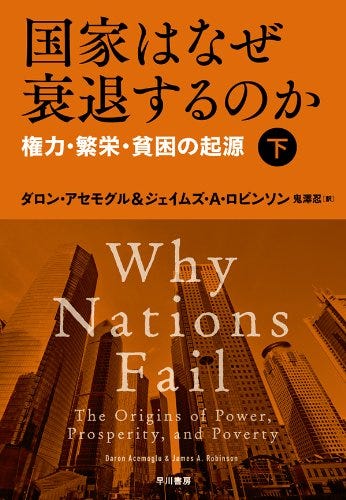国家はなぜ衰退するのか?【読書記録】
皆さんこんにちは。片岡です。
自分は昔から歴史が好きだったのですが、本を読んだり、授業を受けたりしていていつも思っていたことがあります。
「なぜ同じ人間によって運営されているのに、こうも如実に豊かな国と貧しい国に差ができてしまうのか」
という問いです。
例えば朝鮮半島の2国。韓国と北朝鮮は建国から80年ほど経ち、現在は天と地ほどの経済的格差が開いてしまっています。
なぜ、ほぼ同じ民族、文化、歴史を有する国同士でありながら、ここまで差がついてしまっているのでしょうか?
こういった興味深い問いに対して、世界各国、膨大な資料や事例とともに解き明かしていくのが今回紹介する
「国家はなぜ衰退するのか」
です。
「国家はなぜ衰退するのか?」上巻
ダロン アセモグル, ジェイムズ A ロビンソン, 鬼澤 忍 (翻訳)
著者のダロン アセモグル, ジェイムズ A ロビンソン両氏は、本書の内容を含む画期的な経済と政治の関係性に関する一連の研究が評価され、2024年にノーベル経済学賞を受賞しています。
なぜ国境線一本またぐだけで豊かさが変わってしまうのか?―本書が示す、シンプルな仮説
「同じ民族で、文化もほとんど同じ。なのに、なぜか片方は世界有数の豊かな国になり、もう片方は極度の貧困にあえいでいる…。」
これは先ほども例示した現代の韓国と北朝鮮の現実です。
本書内に事例がいくつか出てきますが、国境線を一本またいだだけで、所得、教育、治安などの水準が著しく変わってしまう、アメリカ(アリゾナ州ノガレス)とメキシコ(ソノラ州ノガレス)の事例も程度の差こそあれ似たようなものかもしれません。
地理? 文化? それとも知識の有無?
なぜ国家の間に、ここまで大きな経済的格差が生まれてしまうのでしょうか。
そして、かつて栄華を誇った大国は、なぜ歴史の彼方へと消えていくのでしょうか。
アセモグルとロビンソン両氏による本書では、この壮大な謎に対し、
「その国の『制度』がすべてを決める」
という、驚くほどシンプルで力強い仮説を提示しています。
全ては経済政治の「制度」の差によるもの?
本書の核心的な主張は、国の繁栄と衰退を分けるのは、その国が持つ経済制度と政治制度である、というものです。著者は、世の中の制度を2つのタイプに分類します。
包括的な制度 (Inclusive Institutions) 🤝:
・多くの人々が経済活動や政治に参加できる、開かれた政治経済のシステム。
・財産権が守られ、誰もが自由にビジネスを始められ、努力すれば報われる。
・イノベーションや新しい挑戦が奨励される社会。
・人々への教育や新技術に対する投資が積極的におこり、それらがイノベーションを持たらし、社会を豊かなものにしていく。収奪的な制度 (Extractive Institutions) ⛓️:
・一部の権力者(エリート層)だけが富を独占するために作られた、閉鎖的な政治経済システム。
・エリートは、自分たちの利益を守るために、一般の人々から富を吸い上げ(収奪し)、新しい技術やアイデアの登場を意図的に妨害。
・庶民は、権力者から富がいつ没収されてもおかしくない状況のため、リスクをとって富を増やそうとするような、新技術や事業への投資を行わなくなり、社会は停滞、もしくは衰退していきやすくなる。
つまり、国が豊かになるかどうかは、国民が「誰もが参加できる公平な政治経済システム」を享受しているか、それとも「一部のエリートや特権階級だけが意思決定権をもっているシステム」に縛り付けられているのか、という違いに大きく左右されているのではないかという主張です。
世界史の分岐点:疫病が変えたヨーロッパの運命
では、上記を踏まえて、なぜ一般的な事実として、欧米、とりわけ西欧がその他の地域に比べて早く経済的に発展したのでしょうか。
大きな分岐点として、14世紀にヨーロッパを襲った黒死病(ペスト)による社会変革の事例が紹介されています。
この疫病により、ヨーロッパの人口の実に3分の1から半分が、わずか数年のうちに命を落としたと言われています。
王侯貴族から農民まで、死はあらゆる社会階層を無差別に襲い、それまで絶対的だった封建社会の秩序は、根幹から崩壊の危機に瀕しました。
人口が激減し労働力が希少になると、西ヨーロッパ(特にイングランド)の農民は、より高い賃金と自由を求めて領主と闘い(ワット・タイラーの乱など)、封建制という「収奪的制度」に風穴を開けました。
一方、東ヨーロッパでは逆のことが起こります。
東ヨーロッパの領主たちは、西の同業者よりも組織力で勝っていたため、労働力不足を逆手にとり、農民たちを土地に縛り付ける「再版農奴制」を確立。
「収奪的な制度」をさらに強化してしまいました。
これが現代にもつながる、欧州の東西での経済的格差が開いていくひとつの分岐点となりました。
そして、西ヨーロッパでゆっくりと育まれた「包括的な制度」の萌芽は、17世紀のイギリスで決定的な花を咲かせます。それが、人類の歴史を永遠に変えた産業革命です。
なぜ産業革命はイギリスで起きたのか?
西ヨーロッパでゆっくりと育まれた「包括的な制度」の萌芽は、17世紀のイギリスで花を咲かせます。
それが、人類史でもトップクラスに重要な出来事である産業革命です。
その主役がイギリスだったのは、決して偶然ではありませんでした。
1500年以降、大西洋を横断する貿易が活発になると、イギリスでは国王や旧来の土地貴族だけでなく、新興の商人階級が経済的な力を持つようになります。彼らは貿易で得た莫大な富を元手に、自分たちの財産や事業が国王の気まぐれで脅かされないよう、より強い政治的な発言力を求めるようになりました。この交易の利益が、国王の権力に対抗しうる多元的な権力基盤を生み出し、包括的な制度への変革を後押しする強力な推進力となったのです。
この新しい勢力の台頭がクライマックスに達したのが、名誉革命(1688年)でした。
それまでのイギリスや欧州諸国では、「王は神から権力を授かった特別な存在で、法律よりも上」という考え方(王権神授説)が根強くありました。
王は自分の都合で法律を無視したり、国民から土地や財産を奪ったりすることができたのです。
これに対し、商人階級を含む幅広い勢力が連合して、王の絶対的な権力を制限するために立ち上がります。
そして、血をほとんど流すことなく(そのため「名誉」革命と呼ばれます)、王を追放し、新しい王に「これからは法律と議会に従います」と約束させたのです。
その約束を文書にしたのが、翌年に制定された「権利章典」です。これは、いわば「王を縛るルールブック」のようなものです。主な内容は、
議会の許可なく、王は税金を集めてはいけない。
議会の許可なく、王は法律を作ったり、無効にしたりしてはいけない。
国民は、正当な理由なく逮捕されたり、財産を奪われたりしない。
これにより、イギリスは「人(王)」が支配する国から、「法」が支配する国へと生まれ変わりました。
国民の誰もが、王でさえも、同じルールの下に従うことになったのです。
この「私有財産権」が国によって保証されたことが、決定的に重要でした。
本書は、この「包括的な政治制度」の確立こそが、産業革命の起爆剤だったと主張しています。
「(名誉革命後の)発明家たちは、自分たちの発明が生み出す利益を、国家や個人に収奪される心配がほとんどない包括的な経済制度のもとで活動できるようになった」
ジェームズ・ワットが蒸気機関を改良し、莫大な富を築くことができたのは、「頑張って発明しても、どうせ国王に取られるんだろう」という心配がなく、自分のアイデアと努力が正当に報われると信じられたからです。
公正なルール(制度)が、人々の意欲とイノベーションを爆発させた、これこそが産業革命の本質だったのです。
このイノベーションの連鎖は、既存の産業(例えば手織り職人)を破壊する「創造的破壊」を伴い、ラダイト運動のような反発もありました。
このような、イノベーションによって取り残されてしまう人々への救済策をある程度国や企業が準備することは重要だと思います。これは現代のAI革命にも通じる話ですね。
何はともあれ、このような経緯で包括的な政治制度を育んだイギリス政府は、その後もこのプロセスを止めるのではなく、むしろ促進していくことで世界の覇権国となっていきます。
繁栄のエンジン「イノベーション」を、なぜ権力者は恐れるのか?
では、なぜ良い事だらけのようにみえる「包括的制度」を採用せず、「収奪的制度」に陥ってしまう国が多いのでしょうか。
本書がその理由として挙げるのが、技術革新(イノベーション)に対する「恐怖」です。
経済成長の源泉は、新しい技術やアイデアが古いものを破壊し、社会を前進させる「創造的破壊」にあります。
しかし、収奪的なエリートにとって、この創造的破壊は自らの地位を脅かす「劇薬」でしかありません。
その象徴的な事例が、かつて世界で最も偉大な帝国であったオスマントルコです。
15世紀にヨーロッパで活版印刷技術が発明されたとき、オスマントルコのスルタン(皇帝)は、なんとその技術の使用を法律で禁止してしまいました。
「(収奪的制度のもとでは)新しい技術がもたらす経済的繁栄よりも、それによって安定が損なわれることのほうを、エリートは恐れるのである。」
なぜ当時の世界最先端の大帝国でもあったオスマントルコはこのような選択をしてしまったのでしょうか。
それは、印刷によって知識が民衆に広まれば、既存の権威(聖職者や書記官たち)が失墜し、自分たちの支配体制が揺らぐことを恐れたからです。
彼らは、国の長期的な繁栄よりも、自分たちの権力を守ることを選びました。
少し彼らの肩を持つのであれば、上述したような、イノベーションによる失業問題や価値観の変化などの社会の混乱を避けたかったのかもしれません。
結果的に、西欧が印刷技術によって科学革命や宗教改革を成し遂げ、大きく飛躍していくのを横目に、オスマン帝国は停滞し、やがて「瀕死の病人」と呼ばれるまで衰退していくことになります。
「国家が衰退するのは、収奪的な政治制度が、収奪的な経済制度を支え、経済成長を妨げ、さらには阻止するからだ。」
もちろんオスマン帝国の衰退はこの一例によってのみもたらされたものではないですが、多くの場面でこの収奪的制度が飛躍的な成長の妨げになったと推察されます。
イノベーションの芽を摘み取ってしまう収奪的な政治経済制度こそが、国家を衰退させる根本的な病巣なのだと本書では繰り返し述べられています。
なぜ日本は成功できたのか?「制度」が分けたアジアの運命
歴史を振り返ると、オスマン帝国が印刷機を禁じ、オーストリア皇帝が鉄道建設に反対したように、支配者であるエリート層が自らの権力を脅かす「創造的破壊(イノベーション)」を恐れ、意図的に技術革新を妨げる例は枚挙にいとまがありません。
19世紀の日本が辿った明治維新の道筋は、世界史の中でも極めて特殊な例といえるでしょう。本書でも日本の近代化の事例が詳しく解説されています。
当時、同じく西洋からの強大な圧力に晒された中国(清)は、その後「屈辱の世紀」と呼ばれる長期の停滞と混乱に陥りました。
なぜアジアに数多くある国々のうち日本だけが、5大国入りを果たすほどの、驚異的な近代化を成し遂げることができたのでしょうか?
明治維新が起きた江戸時代の権力者は言うまでもなく徳川幕府です。
徳川幕府が築いた体制もまた、紛れもない「収奪的制度」でした。
武士階級が農民から年貢という形で富を吸い上げ、士農工商という厳格な身分制によって人々の自由な経済活動や社会的な移動を固く禁じられていました。
特に、200年以上にわたる鎖国政策はこれら全てと合わせて、イギリスで起きたような貿易商人や新たな技術者が力をつけてエリート層(武士、幕府)の支配を揺るがす事態を防ぐための、意図的な政策でした。
しかし、本書が「決定的だった」と強調するのが、中国にはなかった「制度のわずかな違い」です。
清の皇帝の権力が国内の隅々まで及ぶ絶対的なものだったのに対し、日本の徳川将軍家の支配は完全ではありませんでした。
特に、薩摩藩や長州藩のような有力な外様大名(藩)は、幕府とは半ば独立した独自の軍事・経済力を保持しており、中央の権力に対抗しうる「多元的」な勢力が国内に存在していたのです。
1853年の黒船来航という「決定的岐路(Critical Juncture)」が幕府の脆弱さを白日の下に晒したとき、この薩長を中心とした勢力が「このままでは日本が植民地にされる」という強烈な危機感から連合し、幕府を打倒しました。これが明治維新です。
ここで最も重要なのは、彼らが単に新しい将軍になったり、自分たちの利益だけを追求したりしたのではない点です。彼らは、自らを含む武士階級全体の特権(旧来の収奪的制度)を、廃藩置県や秩禄処分といった改革によって、自らの手で完全に破壊したのです。
この「自己否定」ともいえる抜本的な政治革命があったからこそ、日本は身分制を撤廃し、国民国家を形成し、包括的な制度を築き、産業革命への道を突き進むことができました。
中国には、中央政府を打倒し、かつ旧来の制度を破壊できるだけの強力な国内連合が存在しなかったのです。この「わずかな違い」が、両国の運命を決定的に分けたと、本書は結論づけています。
なぜ差は広がり続けるのか?好循環と悪循環の罠
一度生まれた制度の差は、なかなか埋まらないどころか、むしろ強化される傾向にあると述べられています。
そこには「好循環(virtuous circles)」と「悪循環(vicious circles)」の力学が働いていると本書は指摘します。
包括的な制度は、権力の集中を防ぎ、自由なメディアを育み、経済を活性化させることで、制度自身をさらに強化していきます(好循環)。
逆に収奪的な制度は、エリートが富と権力を独占し続けるために、さらに収奪的なルールを作り出すことで、永続化してしまうのです(悪循環)。
歴史上の多くの国が、この悪循環の罠から抜け出せずにいます。
ここから、明治維新がいかに稀有な成功例であったかということがわかります。
私たちは今、どちらの制度を築いているのか?
本書は、壮大な歴史、政治、経済の書であると同時に、現代社会(日本も含めて)の私たちの立ち位置を改めて考えさせてくれます。
明治維新で一度は「包括的な制度」への道を力強く歩み始めた日本。
しかしそれから150年以上が経過し、「失われた30年」と呼ばれる長期停滞、硬直化した政治(最近少しずつ風穴が開いてきた感がありますが…)、そして高齢化による社会保障費の増大など、「創造的破壊」を拒む「収奪的」な要素が、社会に根を張り始めている兆候なのかもしれません。
文中で述べたように、収奪的制度による社会はイノベーションが起こりにくいので、見方を変えれば社会的動揺も起こりにくい、常識がひっくり返ることで苦しむ人々が生まれにくい社会という側面もあるかもしれません。
なかなかどっちが100%良いとは言い切れませんが、ファクトフルネス的にはイノベーションが私たちの生活水準を大幅に引き上げてくれたことは間違いないでしょう。
いずれにせよ、これまで説明してきたような歴史の傾向があったということを頭に入れた上で、日々の政治経済ニュースや自分たちが属する国家、組織を俯瞰するとより世界に対する解像度が高まるのではないかと思います。
【まとめ】
豊かな国と貧しい国の差は、地理や文化ではなく、その国の「制度」が決める。
2024年ノーベル経済学賞を受賞したアセモグル、ジョンソン両氏は、制度を「包括的」と「収奪的」に分類。
「包括的制度」は個人の財産権を守り、多くの人々の参加とイノベーションを促し国を豊かにする。
「収奪的制度」はエリートが富を独占し、自らの権力を脅かす「創造的破壊」を恐れ国を衰退させる。
歴史の分岐点(黒死病など)で、制度のわずかな違いが国家の運命を大きく分けた。
イギリスは名誉革命で「包括的制度」を確立し、その後の産業革命に繋がった。
オスマン帝国など多くの国家や組織は「創造的破壊」を恐れ、発展の芽を自ら摘み取り衰退した。
明治維新は、日本が「収奪的制度」から「包括的制度」へ転換した稀有な成功例である。
この成功は、中央権力が絶対的な力を持っていなかったことが大きな要因となった。
一度生まれた差は「好循環・悪循環」によって持続・拡大しやすく、現代世界の格差の根源となっている。
いかがだったでしょうか?
面白い、有益だと思ってくれた方は、是非いいねやご感想をいただけると励みになります。
次回は同じくダロン・アセモグル、 ジェイムズ・A・ロビンソン両氏による「自由の命運」という本を取り上げようと思います。
こちらも今後の国際政治を考えていく上でとても示唆深い一冊になっています。
引き続きよろしくお願いします!!
ダロン アセモグル, ジェイムズ A ロビンソン, 鬼澤 忍 (翻訳)
ダロン アセモグル, ジェイムズ A ロビンソン, 鬼澤 忍 (翻訳)